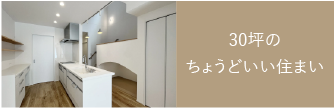窓が少ない家は後悔する?メリット・デメリットから気をつけたいポイントまで解説

注文住宅を建てる際、窓の数や配置は暮らしやすさに大きく影響します。
近年は窓が少ない家も増えており、そのスタイリッシュな外観に惹かれる方は多いのではないでしょうか。
しかし、窓が少ない家にしたことによって、後悔してしまうケースもゼロではありません。
そこで今回は、窓が少ない家のメリットやデメリット、後悔しないためのポイントまで解説します。
| コラムのポイント |
|---|
| ・窓が少ない家は、プライバシーを重視したい方や、デザイン性を追求したい方からニーズが高まっています。 ・窓が少ないことで、断熱性能や防犯性が上がったり、モダンでスタイリッシュなデザインになるなど、さまざまなメリットがあります。 ・閉塞感や圧迫感がある、空気がこもりやすいなどのデメリットもあるため、天井を高くする、窓の配置を工夫するなどの対策が必要です。 |
窓が少ない家の特徴

窓が少ない家は、一般的な住宅と比較すると、外壁面における窓の数や面積が抑えられているのが特徴です。
開口部が少ないため、南や東といった採光しやすい面に集中して窓を配置するか、中庭を設けるなどして、採光と換気を確保するケースが多く見られます。
プライバシーを重視したい場合や、デザイン性を追求したい場合に人気を集めている外観です。
窓が少ない家のメリット

窓が少ない家にする場合、次のようなメリットがあります。
断熱性能が高くなる
窓は壁の10倍ほどの熱が出入りするとも言われており、住宅における熱損失の大きな要因となります。
そのため、窓が少ない家にする場合、断熱性能が高まるのは大きなメリットです。
窓が少ないことによって、外部からの熱の侵入と室内からの熱の流出を抑制でき、冷暖房の効率を上げることができます。
室内の温度を一定に保ちやすくなることで、光熱費の削減にも効果的です。
防犯性が高くなる
窓の数が少ない家では、外部からの侵入経路も少ないため、防犯性が向上します。
家の裏側にあるような人目につきにくい箇所の窓を減らせば、泥棒による侵入リスクの低下にさらに効果的です。
防犯対策を徹底したい場合は、窓の数を最低限に抑え、防犯ガラスや面格子などを活用することもおすすめします。
プライバシーを確保しやすい
窓が少ない家にすることで、外部からの視線が気になりにくく、よりリラックスできるのは大きなメリットです。
隣家との距離が近い場合や、人通りの多いエリア、住宅密集地域の場合はとくに、窓が多いとプライバシーを確保しづらくなります。
そのため、カーテンやブラインドを常時閉めなければならず、家の快適性に影響が出るケースもめずらしくありません。
一方で、窓が少ない場合はプライバシーを尊重しやすく、近隣トラブルの回避にも効果的です。
スタイリッシュでモダンな外観を実現できる
窓が少ない外観に仕上げることで、スタイリッシュかつモダンな印象になる点もメリットです。
色を黒やグレーなどの落ち着いた色合いで統一すれば、さらに洗練された雰囲気を演出できます。
大人でシックな雰囲気や、ミニマルデザイン、インダストリアルなデザインが好みの場合にもおすすめです。
耐震性が向上する
窓やドアなどの開口部は、地震の際に弱点になりやすく、応力集中(局所的に力が大きく加わってしまう現象)の原因になります。
そのため、窓が多い家では構造的な弱点も増えてしまい、耐震性能は下がるのが懸念点です。
一方で窓の少ない家では、応力集中の原因となる開口部が少なく、耐力壁が多くなるため、耐震性能を向上できます。
構造的な安全性を十分に確保したい場合、窓を最小限に抑えるのは効果的なアプローチです。
建築費用を削減できる
窓の数を抑えることによって、窓の設置にかかる材料費や施工費、窓周辺の防水工事や外装工事にかかるコストも削減できるため、建築費用を抑制できます。
スタイリッシュな外観に仕上がりながら、建築費用を抑えられるのは大きなメリットです。
家具の配置がしやすい
窓が少ない家にすると、家具を配置する際に窓の位置を気にする必要が減るため、レイアウトの自由度が上がります。
窓が少ないことで壁面収納も設置しやすくなるため、居住スペースを圧迫せず、空間をより有効活用できるのは大きなメリットです。
窓が少ない家のデメリット

窓が少ない家の場合、防犯性や耐震性能の向上といったさまざまなメリットがある一方で、注意しておきたいデメリットもゼロではありません。
ここからは、窓が少ない家だからこのデメリットを紹介します。
採光が不足し室内が暗くなりやすい
窓が少ない家の場合、自然光が入りづらくなり、室内が暗くなりがちです。
とくに、家の奥まった場所や北側では、日中にもかかわらず常に照明が必要になることも少なくありません。
この場合、光熱費の増加も懸念されます。
自然光を浴びづらいとなると、生活リズムの乱れや、健康面への影響も考えられるため注意が必要です。
換気がしづらく空気がこもりがち
窓が少ないと自然に喚起できず、室内の空気がこもりやすい点には注意しましょう。
とくに梅雨から夏にかけての湿度が高い季節では、湿気がこもってしまうとカビやダニの発生リスクも上がり、健康に被害を及ぼします。
また、外部との温度差が激しい冬場は、十分に換気されないと結露が発生しやすく、建物の劣化につながりかねません。
自然換気が難しいことで、湿気だけでなく調理中の香りやペットのにおいなども滞留しやすいと考えられます。
圧迫感・閉塞感を感じやすい
窓が少ない家では、外の景色が見えづらいだけでなく、換気の悪さも影響して、圧迫感や閉塞感を感じてしまうケースも見られます。
窓が少ない部屋で長時間過ごしていると、人によっては心理的に息苦しさを感じることもめずらしくありません。
住まいの満足度を大きく左右するポイントのため、窓の数を減らしながらも、位置やサイズは十分に考慮する必要があります。
地震や火災発生時のリスクにつながる恐れもある
窓が少ない家では、緊急時の避難経路が限定されてしまいます。
そのため、地震や火災が発生した際には、救急活動に支障を来す恐れもゼロではありません。
窓の数を最低限に抑えながらも、緊急時の安全性や避難経路について十分に考慮しましょう。
窓が少ない家で後悔しないために気をつけたいポイント

「窓が少ない家にしなければよかった」と後悔しないためには、次にあげるいくつかのポイントを押さえておきましょう。
天窓・高窓・中庭を活用する
窓の数を抑えながらも採光を確保するためには、天窓や高窓を活用するほか、中庭を設けましょう。
天窓や高窓は家の上部に設置されているため、自然光を取り入れながらもプライバシーを確保できます。
中庭を設ける場合、家の内側に窓を増やすことができるので、外部からの視線を遮りながらも、採光や通風、開放感を演出可能です。
明るい色の内装を採用する
窓が少ない家で室内の明るさを確保するには、内装を決める際に白やベージュなどの明るい色を基調としましょう。
明るい内装は自然光を反射し、室内全体が明るく感じられると期待できます。
部屋全体を明るいトーンで統一することで、閉塞感や圧迫感も軽減可能です。
仕切りを減らしオープンな間取りにする
室内の仕切りを最小限に抑えたり、可動式の間仕切りを採用することで、自然光が空間全体へ行き渡るように工夫しましょう。
仕切りの少ないオープンな間取りは、自然光が届きやすくなるだけでなく、風も通りやすくなります。
空気がこもりづらくなるため、湿気やにおいが滞留しにくくなるのもメリットです。
風通しを意識した窓配置にする
窓の数を抑えながらも効果的に換気するには、風の通り道を意識して窓を配置します。
対角線上に位置する窓を設置することで、風の通り道を作り、空気を循環しやすくしましょう。
また、高低差のある窓配置にすれば、空気の温度差を利用した重力換気により、効率的に空気を取り込めます。
天井を高くする
窓が少ない家の場合、天井高を上げることによって開放感が生まれ、圧迫感や閉塞感を軽減できます。
天井が高いことで空気も循環しやすくなり、空気やにおいがこもりにくくなる点もメリットです。
窓が少ない家の施工実例

最後に、窓が少ない家の施工実例を紹介します。
どのような外観デザインにしようかお悩みの方は、ぜひ参考になさってください。
窓が少ない家の施工実例①

落ち着いたトーンのグレーで統一し、和モダンな外観に仕上げた実例です。
窓の数を少なく、サイズも小さくすることで、スタイリッシュな印象に仕上がっています。
窓が少ない家の施工実例②

家の正面からは窓が見えない作りとなっている施工実例です。
ファサードの窓を減らして生活感を感じさせないことで、大人なシンプルモダンの雰囲気を演出しています。
窓が少ない家の施工実例③

窓の数とサイズを控えめにすることで、すっきりとした外観になった施工実例です。
窓の配置も工夫することにより、プライバシーを確保しながら、自然光も取り込める家となっています。
窓が少ない家の施工実例④

白い外壁に淡いベージュがナチュラルなアクセントとなっている施工実例です。
窓が少ないデザインにすることで、シンプルで洗練されたイメージが際立っています。
窓が少ない家の施工実例⑤

白を基調とした外壁に、自然素材のドアが印象的な平屋の実例です。
正面部分の窓は最小限に抑え、中庭を設けることによって採光や通風を確保しています。
まとめ
窓が少ない家は、モダンでスタイリッシュな外観に仕上がるため、おしゃれな家を建てたい方にはぴったりのアイデアです。
耐震性能や防犯性の向上など、機能面におけるメリットも少なくありません。
しかし、閉塞感・圧迫感を感じる場合もあるほか、換気がしにくい恐れもあるため、適切な設計と工夫を施す必要があります。
メリットとデメリットを十分に理解した上で、施工業者と相談しながら最適な外観を実現しましょう。