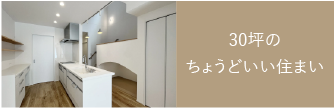断熱等級6の家を建てる|仕様基準・数値や等級7との違い、申請できる補助金も紹介
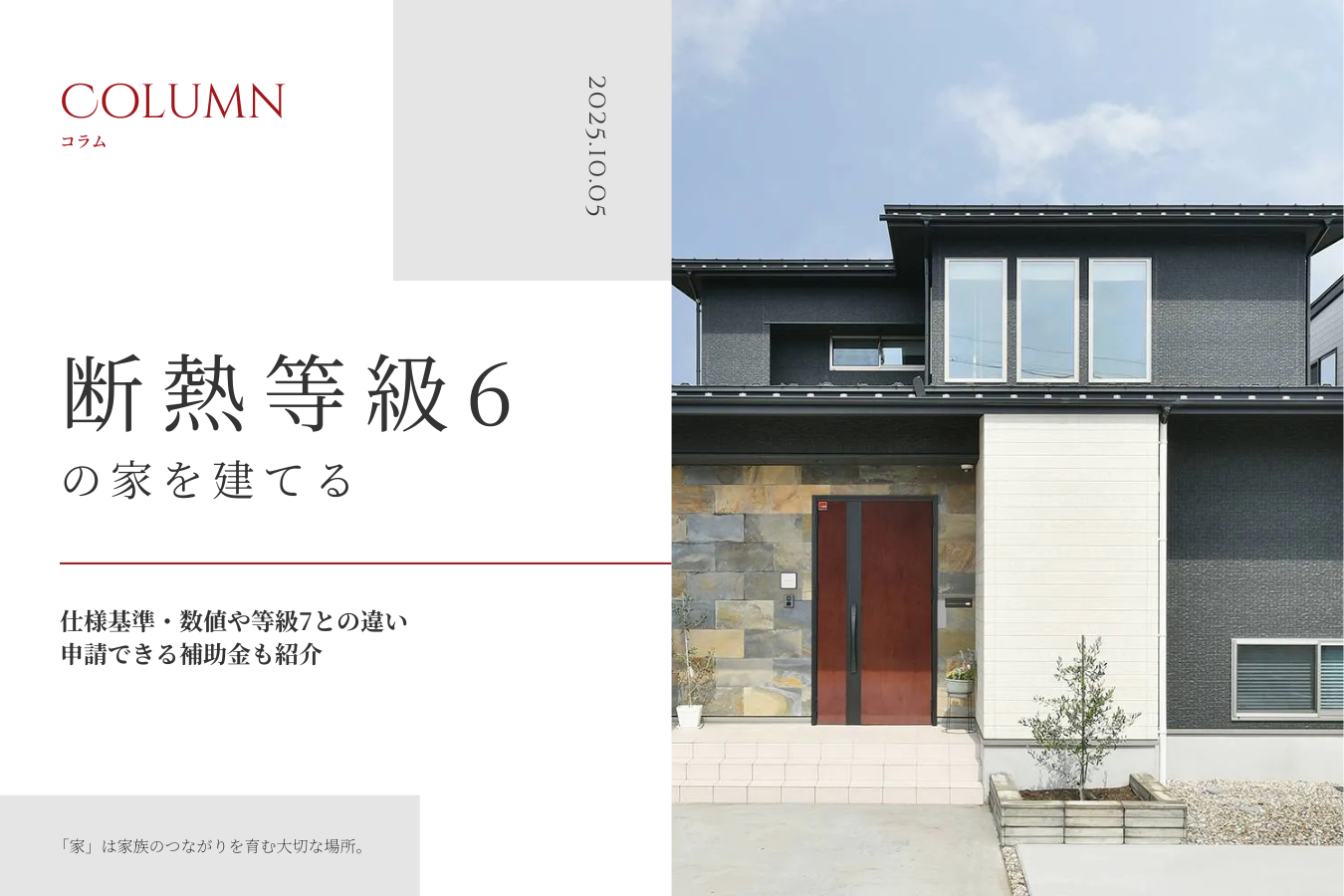
住宅の省エネ基準が、2030年にかけて段階的に上げられています。
今後新たに家を建てる際には、ZEH住宅に相当する断熱等級6以上の家を選んでおきたいところです。
そこで本記事では、断熱等級6の家の仕様基準・数値や、等級7との違い、メリット・デメリットまで解説します。
断熱等級6の家を建てる際に申請できる補助金も紹介するので、ぜひ参考になさってください。
| コラムのポイント |
|---|
| ・断熱等級6の家は、断熱性能が非常に高く、外気温の影響を受けにくい住宅です。 ・断熱等級6の家の場合、季節を問わず室温を快適に保ちやすく、光熱費の削減にも効果的です。 ・建築費が高くなりやすいほか、対応できる施工業者が限られる点には注意しましょう。 |
断熱等級6の家とは

はじめに、断熱等級6とは何か確認していきましょう。
そもそも断熱等級とは
断熱等級とは、住宅の断熱性能を評価する指標です。
等級1から7まで設けられており、等級が高いほど、外からの熱侵入や室内からの熱流出を抑制することを意味します。
|
断熱等級 |
内容 |
|
等級7 |
熱損失等のより著しい削減のための対策が講じられている |
|
等級6 |
熱損失等の著しい削減のための対策が講じられている |
|
等級5 |
熱損失等のより大きな削減のための対策が講じられている |
|
等級4 |
熱損失等の大きな削減のための対策(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令に定める建築物エネルギー消費性能基準に相当する程度)が講じられている |
|
等級3 |
熱損失等の一定程度の削減のための対策が講じられている |
|
等級2 |
熱損失の小さな削減のための対策が講じられている |
|
等級1 |
その他 |
〈出典〉:国土交通省|住宅:法令・制度、省エネ基準等 >住宅性能表示制度における省エネ性能に係る上位等級の創設
新たに家を建てる・購入する際には、断熱等級を確認することで、夏は涼しく冬は暖かい快適な家なのかを判断できます。
断熱等級6の仕様基準・数値
断熱等級6は、等級5を上回る断熱性能として2022年に創設されました。
各等級の基準となる数値は、次の通りに定められています。
|
断熱等級 |
UA値の上限 (W/(㎡・K)) |
ηAC値の上限 |
|
7 |
0.26 |
2.8 |
|
6 |
0.46 |
2.8 |
|
5 |
0.60 |
2.8 |
|
4 |
0.87 |
2.8 |
|
3 |
1.54 |
3.8 |
|
2 |
1.67 |
- |
|
1 |
- |
- |
※記載した値は福井市などの「6地域」に分類された場合に適用される水準
〈出典〉:国土交通省|住宅:法令・制度、省エネ基準等 >住宅性能表示制度における省エネ性能に係る上位等級の創設
ちなみにUA値(ユーエー値)とは、建物の屋根や壁などからどれほど熱が逃げやすいかを示す指標で、ηAC値(イータ・エーシー値)は冷房期にどれほど日射熱が入りやすいかを示す指標です。
|
断熱性能の数値 |
内容 |
|
UA値 |
|
|
ηAC値 |
|
UA値とηAC値の値は、小さければ小さいほど断熱性能が高いことを意味します。
断熱等級6の場合、UA値の上限が0.46、ηAC値の上限が2.8と非常に低く設定されているため、冬に熱が逃げづらく、夏に日射熱が入りづらい家であることがわかります。
また、国土交通省によって提示されている、断熱等級6の家の仕様例は次の通りです。
|
外皮 |
断熱材の仕様例 |
|
天井 |
吹込み用グラスウール18K 270mm |
|
外壁 |
内側:高性能グラスウール16K 105mm 外側:押出法ポリスチレンフォーム3種 25mm |
|
床 |
床 押出法ポリスチレンフォーム3種 95mm |
|
窓 |
窓 樹脂製サッシ+Low-E複層ガラス(G12) |
〈出典〉国土交通省HP>検索窓で「【参考】戸建住宅の断熱仕様の例(6地域・東京等)」と検索
断熱等級6と7の違い
断熱等級よりもさらに断熱性が高い等級7との違いは、次の通りです。
|
項目 |
断熱等級6 |
断熱等級7 |
|
エネルギー消費削減目安(断熱等級4との比較) |
約30%削減 |
約40%削減 |
|
冬の快適性 |
室温がおおむね13℃を下回らず快適に過ごせる |
室温がおおむね15℃を下回らずに快適に過ごせる |
|
夏の快適性 |
就寝時にエアコンを切って眠ることができる |
就寝時にエアコンを切ってもより快適に眠ることができる |
断熱等級の最高位である等級7は、等級6と比較してより室温を安定させますが、その分費用も高くなるため注意が必要です。
コストと性能のバランスが取りやすい等級を選びたい場合、断熱等級6の家をおすすめします。
断熱等級6の家を建てるメリット

断熱等級6の家を建てる場合、どのようなメリットがあるのか一つずつ解説します。
一年中快適に過ごしやすい
断熱等級6の住宅の場合、外気温の影響を受けにくいため、夏の暑さや冬の寒さを軽減できる点がメリットです。
断熱等級6は、HEAT20(一般社団法人 20年先を見据えた日本の高断熱住宅研究会が定めた断熱性能の基準)におけるG2グレードに該当し、冬に暖房を使わずとも、室温が13℃を概ね下回りません。
夏の暑さも最大限に遮断し、冷房効率を上げることができます。
屋根・壁・窓・床まで十分な断熱性能を備えているので、室内温度が安定し、部屋ごとの温度差も軽減可能です。
冷暖房効率が高いため光熱費を削減できる
断熱等級6の家では、高断熱ゆえに冷暖房効率も高く、光熱費の削減にも効果的です。
エアコンによって冷やした/温めた空気が外気の影響を受けにくいため、エアコンの台数が少なくても、室温を快適に保ちやすくなります。
設定気温の下げすぎ・上げすぎも防止でき、断熱等級4の家と比較すると、光熱費を30〜40%ほど削減できるケースもめずらしくありません。
結露が起きにくくカビ・ダニの発生を抑制しやすい
断熱等級6の家では、内壁や窓の表面温度が下がりにくく、結露の発生を抑制できる点もメリットです。
断熱性能が低い家の場合、室内の湿気が壁や窓の表面で冷やされることで、結露が生じてしまいます。
一方、断熱等級6の家であれば、表面温度が下がりにくいため、結露や結露によるカビやダニの繁殖リスクも軽減できます。
ヒートショックのリスク低減につながる
断熱等級6の家では、部屋ごとの温度差も軽減できるため、ヒートショックが発生するリスクを抑制できます。
ヒートショックとは、温度差のある場所へ移動した際に、急激な温度変化によって血圧が急変動し、心臓や血管に負担が生じる現象です。
脳卒中や心筋梗塞を引き起こす恐れもあるため、ご家族の健康を守るためには対策が欠かせません。
断熱等級6の家であれば、ヒートショックの起きやすい浴室、トイレの温度を均一に保ちやすいので、より安全な住まいが手に入ります。
CO2排出削減に寄与できる
断熱等級6の家では、冷暖房によるエネルギー消費量を抑えられるため、CO2の排出削減にもつながります。
太陽光発電を設置し、エネルギーの創出も可能な家にすれば、環境への負担をより軽減可能です。
将来的に資産価値を維持しやすい
断熱等級6の家のような省エネ性能の高い住宅は、今後も市場価値が高まると考えられます。
2021年10月に閣議決定されたエネルギー基本計画等では、2030年度以降に新築される住宅について、ZEH水準の省エネ性能確保を目標とすると決定しました。
断熱等級6の家であれば、2030年以降の省エネ基準にも対応でき、売却時の価格面でも有利になると期待できます。
断熱等級6の家を建てるデメリット

断熱等級6の家を建てる場合、次にあげる3点には注意しましょう。
建築コストが上がる
断熱等級6の家を建てる際には、初期費用が高くなりやすい点に注意しましょう。
断熱等級6の家として承認されるには、UA値の上限が0.46、ηAC値の上限が2.8という厳しい基準を満たす必要があり、そのためには高性能な断熱材が欠かせません。
高断熱な窓ガラスやトリプルサッシなどの建材も高コストです。
さらに、断熱性・気密性を高めるためには、精密な施工技術が求められ、人件費も高くなる傾向があります。
上記を理由に初期費用が高くなりがちですが、その一方で光熱費を削減しやすいため、長期的には回収できる可能性もあります。
気密性と換気設計も重視しないとトラブルにつながる
断熱等級6の家は、優れた気密性を確保するとともに、適切な換気設計が欠かせません。
断熱性能ばかりを優先して気密性が不十分な家では、壁の内部や窓、玄関の土間などで結露が生じやすく、カビやダニが発生するリスクも高まります。
また、換気計画が適切に行われず、気密性が高すぎる家になってしまうと、「空気がこもって息苦しく感じる」「閉塞感を感じる」など、かえって体調不良を招く恐れもゼロではありません。
断熱性能だけでなく、気密性能や換気設計まで十分に考慮することで、さまざまなトラブルも未然に防ぎましょう。
対応できる会社が限られる
断熱等級6の家は、どの工務店・ハウスメーカーも対応できるわけではありません。
断熱等級6の条件を満たす家にするには、豊富な専門知識と高度な設計力、経験に基づく精密な施工技術が求められ、そのレベルに対応できる工務店が少ないためです。
問題なく対応できる会社を選ぶには、断熱等級6以上の省エネ住宅を建てた実績が豊富で、なおかつ専門的な知識と技術を有した施工業者を選びましょう。
依頼を検討する段階で、実際の施工事例や、UA値・ηAC値などの数値もあわせて確認できると安心です。
リョーエンホームの提供する「レコメンドスタイル」の家では、断熱等級6でありながら、坪単価82.5万円(税込)〜と手の届きやすい価格を実現しています。
コストと性能のバランスが良い家を建てたい方は、こちらより詳細をごらんください。
断熱等級6の家を建てる際に申請できる補助金

断熱等級6の家を建てる際、気になるのが建築コストの高さです。
できる限り費用を抑えたい場合、補助金を申請して実質的負担を抑えることをおすすめします。
2025年10月現在で、断熱等級6以上の家を建てる際に申請できる補助金は次の2つです。
|
制度名 |
対象者 |
対象となる住宅と補助額(一戸あたりの額) |
|
ZEH支援事業 |
・新築戸建住宅を建築・購入する個人 ・新築戸建住宅の販売者となる法人 |
ZEH/Nearly ZEH/ZEH Oriented:55万円+α ZEH+/Nearly ZEH+:90万円+α(※1) |
|
子育てグリーン住宅支援事業 |
・0〜18歳未満の子どもがいる世帯 ・夫婦どちらかが39歳以下の若者夫婦世帯 ・GX志向型住宅のみ、すべての世帯 |
GX志向型住宅:160万円 |
※1 〈参照〉戸建ZEH|ZEH補助金>パンフレット「一般社団法人 環境共創イニシアチブ|2025年の経済産業省と環境省のZEH補助金について」
※2 〈参照〉対象要件の詳細【注文住宅の新築】|子育てグリーン住宅支援事業
また、補助金を申請したい場合は申請期限に注意しましょう。
ZEH支援事業は2025年12月12日(金)17:00、子育てグリーン住宅支援事業は2025年12月31日(水)が締切とされていますが、どちらも予算に達したら前倒しで受付終了となります。
申請期限に間に合うかと思いきや、すでに受付が終了している恐れもあるので、できる限り早めに準備を進めておくと安心です。
まとめ
断熱等級6の家は、冬も室温がおおむね13℃を下回らず、夏は空調を使用しなくても寝やすいなど、断熱性能が非常に優れています。
しかし、対応できる工務店やハウスメーカーは限られており、精密な施工技術が求められるため、建築時の施工業者選びは慎重に行いましょう。
リョーエンホームでは、断熱等級6の家の施工実績も豊富なため、福井で注文住宅を建てたい方はお気軽にご相談ください。